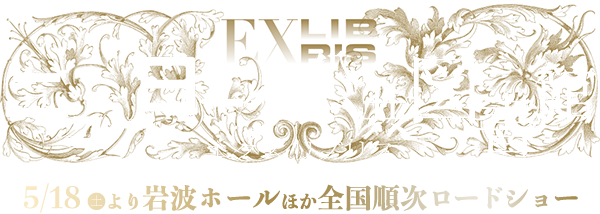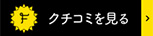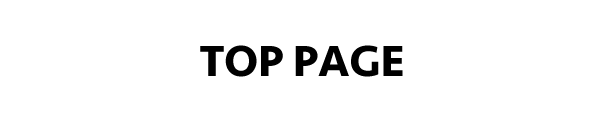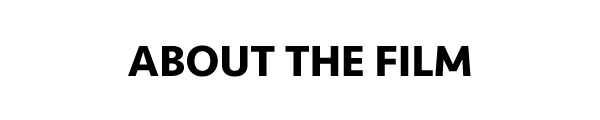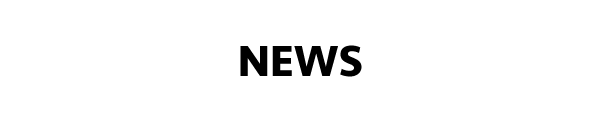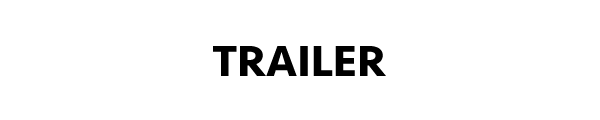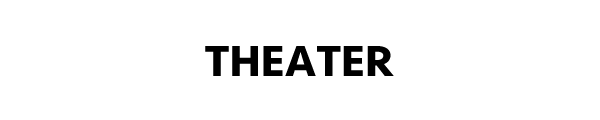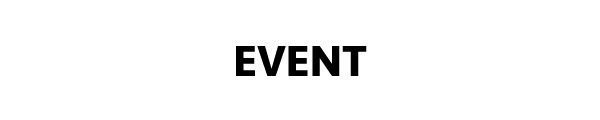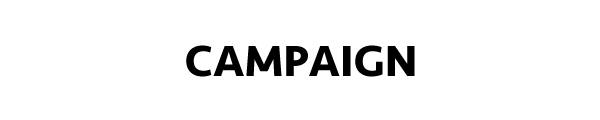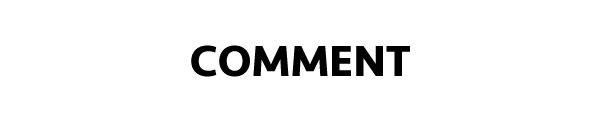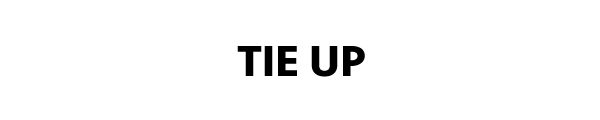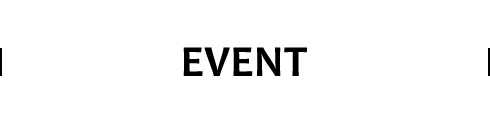
『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』 公開記念パネルディスカッション
ニューヨーク公共図書館と<図書館の未来>
ニューヨーク公共図書館と<図書館の未来>
ニューヨーク公共図書館幹部役員キャリー・ウェルチさんが来日し、日本の図書館関係者とのディスカッションに参加しました。
社会のデジタル化がすすみ、全世界の図書館が新しいあり方を模索する中で、ニューヨーク公共図書館(NYPL)は、驚くほどに多彩な活動を成功させ、世界中から注目されている図書館です。彼らは、その活動を実現するために、いかに認知度をあげ、いかに支援者を獲得しているのでしょうか。アカデミー賞名誉賞受賞の巨匠フレデリック・ワイズマン監督が、ニューヨーク公共図書館の舞台裏に迫った傑作ドキュメンタリー『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』の公開を記念し、ニューヨーク公共図書館幹部キャリー・ウェルチさんが来日。第一部ではキャリーさんとともに、ニューヨーク公共図書館を取材した名著で知られる在米ジャーナリスト・菅谷明子さんをお迎えし、トークと映画の紹介。第二部では、キャリーさん、菅谷さんと日本の図書館関係者、研究者など豪華パネラーが参加したパネルディスカッションが開催されました。
開催日時:2019年4月9日(火)会場:日比谷図書文化館コンベンションホール
■ 第一部:トークと映画の紹介
動画は下記よりご覧いただけます。■ 第二部:パネルディスカッション
動画は下記よりご覧いただけます。パネルディスカッションは抄録を下記に掲載します。
登壇者
パネラー:キャリー・ウェルチ(ニューヨーク公共図書館渉外担当役員)パネラー:菅谷 明子(在米ジャーナリスト/ハーバード大学ニーマン・ジャーナリズム財団役員)
パネラー:田中 久徳(国立国会図書館総務部部長)
パネラー:越塚 美加(学習院女子大学国際文化交流学部教授)
モデレーター:野末 俊比古(青山学院大学教育人間科学部教授)
キャリー・ウェルチ通訳:横田佳代子
登壇者の詳しいプロフィールはこちら
[抄録]
多様な「情報」を積極的に集めて提供するニューヨーク公共図書館(菅谷)
野末:ディスカッションの趣旨ですが、日米を比較して「アメリカはこうだ」「日本はこうだ」、そして「アメリカはいいなぁ」「日本もこうなればいいなぁ」と終わらせず、日米に違いがあることは認めたうえで、日本としてどういったところを手にできるかを考えていこう、ということです。今日来場されている皆さまも、我々登壇者も、図書館の可能性についてあらためて知る、考えるきっかけをつくることができればいいのではないか、そしてそれぞれの仕事や生活に何かヒントになるところが一つでも二つでも伝わっていけばいいのではないかと思っています。
今日は図書館関係の方も多くいらっしゃっていますので、今日のテーマである「図書館の未来」、これから図書館はどうしていけばいいのか、どういうことを考えていけばいいのか、そのために我々は何ができるのかというきっかけ、ヒント、あるいはひらめきのようなものを一つでも提供できればと思います。ですので、何かテーマを決めて結論を出そうというのではなく、いろいろな立場からいろいろな観点から論点を出しあって、皆さんそれぞれが持ち帰っていただければと考えています。
日本では「ニューヨーク公立図書館」と訳されることがまれに見受けられますが、「公立」ではなく、やはり「公共」図書館なのです。パブリックとプライベートの協働関係、パートナーシップ関係で運営されているというところが、もっぱら税金で運営されている日本の「公立」図書館──運営形態はいろいろですが──とは少し仕組みが違うというところは前提としてお話ができればと思います。日本の場合には、市町村の図書館、都道府県の図書館、そして国立国会図書館のように、「公立」といっても役割が違うことも前提として踏まえていければと思っています。
まず、映画をご覧になってパネリストの皆さんが何を受け取ったか、ということをお話しいただこうと思います。最初に菅谷さんから──米国の図書館に詳しいジャーナリストとして──お願いします。
菅谷:私自身はもともとメディア研究をやってきた人間なので、図書館もどちらかというと「市民社会における情報インフラ」というような視点から捉えていまして、多分そこが、これまで図書館関係者によって出版された本や論文で言及されてきたニューヨークの公共図書館の描き方とは違っていたのかな、と思っています。
また、先ほど野末さんからご紹介があった点に少し補足を加えさせていただきますが 、アメリカのほとんどの公共図書館も税金で運営されていますので、その点でも「ニューヨーク公共図書館」は世界的にも非常にユニークです。それから、ふたつの異なるシステムから成り立っている点も大きな特徴です。「研究図書館」は4つの専門図書館を抱え、こちらの財源は寄付金が大きな割合を占め、「地域分館」は市からの資金もあります。そのあたりはキャリーさんからお話いただいたほうがいいと思います。
それから、ニューヨーク公共図書館というのは、規模やビジョン、キャリーさんのような優れた業績を持たれている方をヘッドハントしてくることからもわかるように、非常に専門性の高い人たちがスタッフとして働いています。私たちが日本で一般的にイメージするような公共図書館というよりは、ニューヨークの似たような公共施設で言えば、メトロポリタン美術館や近代美術館みたいな感じで、アメリカの典型的な図書館ではない、というか、それを越えているような存在だというのは、今日の議論の際に、我々の頭の片隅に置いておいてもいいかなと思います。
映画の感想ですが、とりわけこの数十年ほどは情報過多時代と言われ、検索をすれば何でもわかると一般に信じられてきていますが、この映画をみると「情報」の定義がいかに広いか、ということに改めて気付かされます。例えば日本の図書館ですと、既に出版物として刊行されたものを図書館が保管して閲覧したり貸出しできるようにすることが主な仕事になっていると思いますが、先ほどのダイジェスト版でみた「ピクチャー・コレクション」なども一例ですが、図書館自らが企画を立てて、情報を集めて編集するなど、新たなものを生み出し提供して行くという点が、非常に示唆に富むと思っています。
ピクチャー・コレクション以外にも、例えば、舞台芸術図書館という専門図書館があります。私は音楽家や映画俳優が「勉強」するとは今まであまり考えたことがありませんでしたが、舞台芸術図書館に行くと、たくさんの楽譜があって、それを見ながらオペラ歌手の方が歌の練習をしていたり、俳優さんが方言の音源を借りてオーディションに備えていたり。そうした役割もあって、特にこの図書館は印刷物に止まらない実に多様な形態のコレクションを提供しています。そうすると、私たちが考えている 図書館にある「情報」というのは非常に限られたものを定義していると思わずにはいられなくなります。
この映画の端々には、私たち自身も気が付いていないタイプの「情報」、あるいはそれにまつわるサポートがまだまだ必要で、ニューヨーク公共図書館は自らリーダーシップを取って、多様な「情報」を積極的に集め、提供することで、市民の幅広いニーズに応えているのではないか、ということに改めて気付かされました。
野末:気づいていないニーズというところはポイントになると思いますので、あとで少し掘り下げていければと思います。続いて、田中さんは国立国会図書館にお勤めです。図書館にお勤めの立場から、普段お考えのことなども踏まえて、お話しいただければと思います。
図書館が社会のインフラで、電子の時代になれば、ますますその情報基盤として役割を果たさなければならないという認識を強く持っています。この映画は大変素晴らしいと思うのですが、ニューヨーク公共図書館自体もすごく素晴らしいし、この映画も大変素晴らしい。ニューヨーク公共図書館ということで言えば、私たちも、菅谷さんの本が出てすぐに読んで皆、感動しましたし、国会図書館からもSIBLなどに出張で何人も行っています。そして、私たちの閲覧室、科学技術・経済情報室という専門室があるのですが、そういったところのサービスを考えるのにも随分参考にさせていただいています。
一つ付け足しますと、一部で(菅谷さんから)組織に属さない人がデータベース(にアクセスするのが難しい)という話がありましたが、国会図書館も契約でデータベースをたくさん導入していますし、電子ファイルもたくさんあり、どこの組織に属さなくても無料で使えます。これは宣伝ですが、どんどん使っていただきたいと思います。
映画に戻りますが、キーワードは「民主主義を支える柱」という部分だと私は思います。最初がリチャード・ドーキンスの場面から始まるのもすごい。思想家であり、科学者であり、そうした人が直接市民に語りかける。こういうことができる図書館がいかに素晴らしいかと本当に思いました。
それからもう1点、やはりデジタル化ということで、幹部の方たちが議論する場面が何度も出てきますが、その中で電子情報には色んな課題があります。映画の中で、蔵書をデジタル化しても必ずしも全部インターネットで出せるというわけでもない、というところも出てきます。私どもも同じような問題に直面していますが、そこを機能させ、電子時代、インターネットのある中で、図書館とはどういう役割を果たすのか。それが今の一番の課題だと思います。インターネットがあれば図書館はもういらないという話ではなく、逆に、インターネットに繋いだからこそ、場所としての図書館も含めて、図書館の役割がどんどん大きくなっている、というのが大きな印象です。
野末:デジタル社会の図書館の役割というのは、会場の皆さんも興味のあるところだと思いますので、のちほど掘り下げてみようと思います。それでは、図書館情報学の研究者の立場から、越塚さん、お願いします。
残念ながら、映画ではあまり取り上げられていませんが、ニューヨーク公共図書館には、SIBL──Science, Industry and Business Library──という図書館があり、1997年か1998年か、そこができてすぐに参りました。こんな素晴らしいサービスがあるのかと思っていろいろと考えることがあり、そうしたことも研究のテーマに繋がっています。
映画の話では、ダイジェストにも少し出てきましたが、ニューヨーク公共図書館は、ニューヨーク市という「官」からと、そして(「民」からの)寄付から成り立っている予算でサービスを展開していく。そのことが映画では、繰り返し、繰り返し、出てまいります。そのことはとても印象的なのですが、もう一つ、そのお金をどうやって使おうかという時に、このお金は何のためにどこから得て来たか、という意識を強くもちながらサービスを展開していく。それから、「民」からの寄付金による予算の割合が増えれば増えるほど、そのサービスが重要だと考えられて、ニューヨーク市からの予算も増えていくと話す場面が出てきます。それは、なかなか日本では考えられないと私は思ったのですが、一方で、どこから得たお金だからどういう風に使っていこうと、その財源を還元していく。
日本の公共図書館の場合には、税金によって成り立っているのがほとんどですので、その税金を払った人はどういう人たちで、ではどういうことを返していこうかという考え方がされているとは思うのですが、改めて大変重要だと思いました。
先ほど申し上げたSIBLというビジネス関係のことを扱っている図書館は、ニューヨーク公共図書館の本館より少しウォールストリート側、34丁目にあります。1997年に行った時にすごくびっくりしたのが、「こういう講習会があって皆さん申し込むことができます、無料です」と、20年前の話ですから、自分でウェブサイトを立ち上げようとしている人のための講座や、データベースを仕事のために使おうとしている人たちのための講座などがたくさんリストアップされていたのですが、その開始時間に驚きました。夕方の6時始まりというのが非常に多かったのです。どうしてですか?とお聞きすると、その時に返ってきた答えが、この図書館をつくるにあたっては、ウォールストリートからたくさんの寄付を受けた、だからこのお金はサービスのかたちでウォールストリートの利用者に還元するべきである、と。そうすると、仕事が終わってから参加する講座があってほしい。だから6時から始めることになったんですよ、と特別なことでもなんでもなくお話されるわけなんです。そのサービスの姿勢、そこのところに非常に感銘をうけました。
それが私にとっては一番最初に、ニューヨーク公共図書館を訪れた時の非常に強烈な印象です。その哲学---と言っていいと思うのですが---その考え方は、ダイジェストの中だけでも、かなり明確に出てきていると思いますが、映画をご覧いただくと、ずっとその話が出てきます。サービスをどう組み立てていくか、あるいは、寄付をどこから集めてくるか、どういう目的で集めてくるか、市にどのように予算要求をするか、どこから財源を得ているのか、どのサービスのためにとった予算なのかということをものすごく真剣に考えている。
そして、そういうことを組み立てていく時に、図書館畑でずっときた方ではなく、キャリーさんのように資金集めについてきちんと説明できる専門家が必要だというのはよく分かる話ですし、また、雇用することによってニューヨーク公共図書館全体のサービスを向上させていくという考え方がとてもよく分かる、という印象をもちました。
野末:ニーズとサービスは、よく我々は対で語りますが、予算とか財源ということも考えあわせていくと、多様な議論が日本でもできるかと思います。3名のパネリストから、映画からどんなことを受けとめたかをお話しいただきましたので、キャリーさんに、それを受けて感想・意見・補足などをお願いします。
映画本編に出ていないことを残念に思ってくださったことにもお礼申し上げます。確かに残念ですが、実は映画の中で出てくる分館は12か所しかありません。88か所のうちの12か所しか入っていない。私どもの誇りとしているSIBLも残念ながら落とさなければいけなかったのですが、今褒めてくださったことをSIBLの皆に伝言いたします。
資金についてですが、官民のパートナーシップというのは過去25年余に渡り、図書館だけではなく、いろいろな組織において重要な主流のやり方になってきています。1年の予算はおよそ3億7千万ドル。その約50%が、ニューヨーク市からの公的資金です。そして、年間2千万ドルがニューヨーク州のほうからの資金です。連邦政府からは元々いただいておりません。ましてや今の時代、いただかなくて当たり前という人選ですが(笑)。
研究図書館のために州からの2千万ドル。そして市からの資金。残りの資金は民間からいろいろなかたちで得ています。ニューヨーク公共図書館は、ブルックリンとクイーンズにもそれぞれの図書館網があり、そこと提携し、力をあわせて市長と市議会に対して予算折衝を行います。市当局へての働きかけというのは、はっきり申し上げてまったく楽しくありません。成果もなかなかあがりません。ブルームバーグ市長の時代には、基本的に市は「お金をくれない」「横ばい」「伸びない」、そうした状況が続いて、これを私たちはよく「ダンスを踊っている」と例えていました。ああ言えばこう言う、やりとりを重ねても、なかなか成果があがりませんでした。
今の市長になり、彼が掲げる重要目標と私たちがやっていることが見事に重なったことで、具体的な予算獲得につながっています。例えば市長は、政策の柱の一つとして、早期から読み書きを教えることを重要としていますが、私たちが、よちよち歩きの幼児から識字教室をやっていることで、市長としては公約を果たすことにつながる。これを大いに成果として主張して、予算獲得につなげています。
また、民間からと一口に言いましても、だいたい年間で合計1億ドルを、いろいろな方々──要するに政府以外──から、本当にありとあらゆる方からいただいています。5ドルくらいのごく少額でもずっと支えてくださる方もいらっしゃいますし、大々的に寄付してくださる方もいらっしゃいます。ありがたいのは、生きていく上でものすごく助かった、これで命がつながったと思ってくださる方々がいることです。
具体的に言いますと、ニューヨーク公共図書館があったから読み書きを身につけることができた、英語で読み書きができるようになったから仕事が見つかった、だから今生きている、今の自分がある、という方が、必ず何らかのかたちで返してくださっています。
そしてもう一つ、「公共=パブリック」の意味についても皆さんが説明してくださいましたが、端的に言いますと、皆の税金で支えているから皆のものだよね、ということです。パブリックというのは我々ニューヨークに暮らす人間全員のことを指しているということが、意識として、図書館は自分たちのものなんだ、皆のものなんだ、と思って下さっているんだと思います。
いろいろな財団、そして企業からお金を頂戴することもありますが、一番大きいのは個人からのご寄付なのです。これは篤志家からのチャリティ、フィランソロピーと言いますが、そうした慈善の一環として、どこかに資産を提供する、もしくは寄付をするというのは、アメリカのDNAの一部と言っても差し支えありません。また、あまり皆さんおっしゃいませんが、税金上有利だということもあります。今まで個人からいただいた最大のご寄付は1億ドルですが、5ドルくらいの寄付というのも大変ありがたいし、それも常時くださっている方々が沢山いるということは大事です。
そのために私どもは専門家のチームをかなり整備していますが、忘れてはいけないのは、民間からの寄付を募るというのは、もの凄く専門性の高い、そして時間もかかる、何年間もの関係づくりが必要だということ、断られてもめげない心の強さ、これが絶対必要だということです。お金の話で頭を使いきってしまいました。後の質問はピンポイントでいただくほうがいいかもしれません(笑)。
今日は図書館関係の方も多くいらっしゃっていますので、今日のテーマである「図書館の未来」、これから図書館はどうしていけばいいのか、どういうことを考えていけばいいのか、そのために我々は何ができるのかというきっかけ、ヒント、あるいはひらめきのようなものを一つでも提供できればと思います。ですので、何かテーマを決めて結論を出そうというのではなく、いろいろな立場からいろいろな観点から論点を出しあって、皆さんそれぞれが持ち帰っていただければと考えています。
日本では「ニューヨーク公立図書館」と訳されることがまれに見受けられますが、「公立」ではなく、やはり「公共」図書館なのです。パブリックとプライベートの協働関係、パートナーシップ関係で運営されているというところが、もっぱら税金で運営されている日本の「公立」図書館──運営形態はいろいろですが──とは少し仕組みが違うというところは前提としてお話ができればと思います。日本の場合には、市町村の図書館、都道府県の図書館、そして国立国会図書館のように、「公立」といっても役割が違うことも前提として踏まえていければと思っています。
まず、映画をご覧になってパネリストの皆さんが何を受け取ったか、ということをお話しいただこうと思います。最初に菅谷さんから──米国の図書館に詳しいジャーナリストとして──お願いします。
菅谷:私自身はもともとメディア研究をやってきた人間なので、図書館もどちらかというと「市民社会における情報インフラ」というような視点から捉えていまして、多分そこが、これまで図書館関係者によって出版された本や論文で言及されてきたニューヨークの公共図書館の描き方とは違っていたのかな、と思っています。
また、先ほど野末さんからご紹介があった点に少し補足を加えさせていただきますが 、アメリカのほとんどの公共図書館も税金で運営されていますので、その点でも「ニューヨーク公共図書館」は世界的にも非常にユニークです。それから、ふたつの異なるシステムから成り立っている点も大きな特徴です。「研究図書館」は4つの専門図書館を抱え、こちらの財源は寄付金が大きな割合を占め、「地域分館」は市からの資金もあります。そのあたりはキャリーさんからお話いただいたほうがいいと思います。
それから、ニューヨーク公共図書館というのは、規模やビジョン、キャリーさんのような優れた業績を持たれている方をヘッドハントしてくることからもわかるように、非常に専門性の高い人たちがスタッフとして働いています。私たちが日本で一般的にイメージするような公共図書館というよりは、ニューヨークの似たような公共施設で言えば、メトロポリタン美術館や近代美術館みたいな感じで、アメリカの典型的な図書館ではない、というか、それを越えているような存在だというのは、今日の議論の際に、我々の頭の片隅に置いておいてもいいかなと思います。
映画の感想ですが、とりわけこの数十年ほどは情報過多時代と言われ、検索をすれば何でもわかると一般に信じられてきていますが、この映画をみると「情報」の定義がいかに広いか、ということに改めて気付かされます。例えば日本の図書館ですと、既に出版物として刊行されたものを図書館が保管して閲覧したり貸出しできるようにすることが主な仕事になっていると思いますが、先ほどのダイジェスト版でみた「ピクチャー・コレクション」なども一例ですが、図書館自らが企画を立てて、情報を集めて編集するなど、新たなものを生み出し提供して行くという点が、非常に示唆に富むと思っています。
ピクチャー・コレクション以外にも、例えば、舞台芸術図書館という専門図書館があります。私は音楽家や映画俳優が「勉強」するとは今まであまり考えたことがありませんでしたが、舞台芸術図書館に行くと、たくさんの楽譜があって、それを見ながらオペラ歌手の方が歌の練習をしていたり、俳優さんが方言の音源を借りてオーディションに備えていたり。そうした役割もあって、特にこの図書館は印刷物に止まらない実に多様な形態のコレクションを提供しています。そうすると、私たちが考えている 図書館にある「情報」というのは非常に限られたものを定義していると思わずにはいられなくなります。
この映画の端々には、私たち自身も気が付いていないタイプの「情報」、あるいはそれにまつわるサポートがまだまだ必要で、ニューヨーク公共図書館は自らリーダーシップを取って、多様な「情報」を積極的に集め、提供することで、市民の幅広いニーズに応えているのではないか、ということに改めて気付かされました。
野末:気づいていないニーズというところはポイントになると思いますので、あとで少し掘り下げていければと思います。続いて、田中さんは国立国会図書館にお勤めです。図書館にお勤めの立場から、普段お考えのことなども踏まえて、お話しいただければと思います。
国立国会図書館も同様に直面しているデジタル化の問題(田中)
田中:皆さん、国会図書館はご存知だと思いますが、国の図書館ですけれど、アメリカの戦後の改革の中で、アメリカの議会図書館を模倣したかたちでできました。国立図書館が議会図書館である、というのはアメリカと日本だけです。そういう意味で、アメリカの制度を私たちも常に意識しながら仕事をしているというところはあります。あまり知られていませんが、国の予算だけでなく、寄付金も受ける、という法律の条文も──なかなか機能はしてないですけれど──あります。それから私は、図書館資料のデジタル化というのをずっとやってきていて、デジタル社会で、あるいは電子情報の中で図書館の役割はどうなっていくのかというのは、常に考え続けてきているところではあります。図書館が社会のインフラで、電子の時代になれば、ますますその情報基盤として役割を果たさなければならないという認識を強く持っています。この映画は大変素晴らしいと思うのですが、ニューヨーク公共図書館自体もすごく素晴らしいし、この映画も大変素晴らしい。ニューヨーク公共図書館ということで言えば、私たちも、菅谷さんの本が出てすぐに読んで皆、感動しましたし、国会図書館からもSIBLなどに出張で何人も行っています。そして、私たちの閲覧室、科学技術・経済情報室という専門室があるのですが、そういったところのサービスを考えるのにも随分参考にさせていただいています。
一つ付け足しますと、一部で(菅谷さんから)組織に属さない人がデータベース(にアクセスするのが難しい)という話がありましたが、国会図書館も契約でデータベースをたくさん導入していますし、電子ファイルもたくさんあり、どこの組織に属さなくても無料で使えます。これは宣伝ですが、どんどん使っていただきたいと思います。
映画に戻りますが、キーワードは「民主主義を支える柱」という部分だと私は思います。最初がリチャード・ドーキンスの場面から始まるのもすごい。思想家であり、科学者であり、そうした人が直接市民に語りかける。こういうことができる図書館がいかに素晴らしいかと本当に思いました。
それからもう1点、やはりデジタル化ということで、幹部の方たちが議論する場面が何度も出てきますが、その中で電子情報には色んな課題があります。映画の中で、蔵書をデジタル化しても必ずしも全部インターネットで出せるというわけでもない、というところも出てきます。私どもも同じような問題に直面していますが、そこを機能させ、電子時代、インターネットのある中で、図書館とはどういう役割を果たすのか。それが今の一番の課題だと思います。インターネットがあれば図書館はもういらないという話ではなく、逆に、インターネットに繋いだからこそ、場所としての図書館も含めて、図書館の役割がどんどん大きくなっている、というのが大きな印象です。
野末:デジタル社会の図書館の役割というのは、会場の皆さんも興味のあるところだと思いますので、のちほど掘り下げてみようと思います。それでは、図書館情報学の研究者の立場から、越塚さん、お願いします。
「官」と「民」からの予算で展開するサービスへの意識(越塚)
越塚:私は図書館員として働いた経験はなく、学生時代に図書館情報学を勉強し、そのまま研究の道に入りました。最近ずっと関心を持っておりますのが、日本の公共図書館の「課題解決型サービス」──地域のさまざまなニーズを掘り起こし、そのニーズに沿ったサービスを展開していきましょうということ──で、主にビジネス部門・健康部門・法律部門等々が柱として選ばれ、その中のビジネス部門というのは公共図書館ではそれまでごく限られた図書館でしか扱ってこなかったものでしたので、どういう風に展開して、どういう風に受け入れられていくのだろうかということに非常に興味を持ち、グループで、もう10年以上、研究してまいりました。残念ながら、映画ではあまり取り上げられていませんが、ニューヨーク公共図書館には、SIBL──Science, Industry and Business Library──という図書館があり、1997年か1998年か、そこができてすぐに参りました。こんな素晴らしいサービスがあるのかと思っていろいろと考えることがあり、そうしたことも研究のテーマに繋がっています。
映画の話では、ダイジェストにも少し出てきましたが、ニューヨーク公共図書館は、ニューヨーク市という「官」からと、そして(「民」からの)寄付から成り立っている予算でサービスを展開していく。そのことが映画では、繰り返し、繰り返し、出てまいります。そのことはとても印象的なのですが、もう一つ、そのお金をどうやって使おうかという時に、このお金は何のためにどこから得て来たか、という意識を強くもちながらサービスを展開していく。それから、「民」からの寄付金による予算の割合が増えれば増えるほど、そのサービスが重要だと考えられて、ニューヨーク市からの予算も増えていくと話す場面が出てきます。それは、なかなか日本では考えられないと私は思ったのですが、一方で、どこから得たお金だからどういう風に使っていこうと、その財源を還元していく。
日本の公共図書館の場合には、税金によって成り立っているのがほとんどですので、その税金を払った人はどういう人たちで、ではどういうことを返していこうかという考え方がされているとは思うのですが、改めて大変重要だと思いました。
先ほど申し上げたSIBLというビジネス関係のことを扱っている図書館は、ニューヨーク公共図書館の本館より少しウォールストリート側、34丁目にあります。1997年に行った時にすごくびっくりしたのが、「こういう講習会があって皆さん申し込むことができます、無料です」と、20年前の話ですから、自分でウェブサイトを立ち上げようとしている人のための講座や、データベースを仕事のために使おうとしている人たちのための講座などがたくさんリストアップされていたのですが、その開始時間に驚きました。夕方の6時始まりというのが非常に多かったのです。どうしてですか?とお聞きすると、その時に返ってきた答えが、この図書館をつくるにあたっては、ウォールストリートからたくさんの寄付を受けた、だからこのお金はサービスのかたちでウォールストリートの利用者に還元するべきである、と。そうすると、仕事が終わってから参加する講座があってほしい。だから6時から始めることになったんですよ、と特別なことでもなんでもなくお話されるわけなんです。そのサービスの姿勢、そこのところに非常に感銘をうけました。
それが私にとっては一番最初に、ニューヨーク公共図書館を訪れた時の非常に強烈な印象です。その哲学---と言っていいと思うのですが---その考え方は、ダイジェストの中だけでも、かなり明確に出てきていると思いますが、映画をご覧いただくと、ずっとその話が出てきます。サービスをどう組み立てていくか、あるいは、寄付をどこから集めてくるか、どういう目的で集めてくるか、市にどのように予算要求をするか、どこから財源を得ているのか、どのサービスのためにとった予算なのかということをものすごく真剣に考えている。
そして、そういうことを組み立てていく時に、図書館畑でずっときた方ではなく、キャリーさんのように資金集めについてきちんと説明できる専門家が必要だというのはよく分かる話ですし、また、雇用することによってニューヨーク公共図書館全体のサービスを向上させていくという考え方がとてもよく分かる、という印象をもちました。
野末:ニーズとサービスは、よく我々は対で語りますが、予算とか財源ということも考えあわせていくと、多様な議論が日本でもできるかと思います。3名のパネリストから、映画からどんなことを受けとめたかをお話しいただきましたので、キャリーさんに、それを受けて感想・意見・補足などをお願いします。
「公共=パブリック」というのは我々ニューヨークに暮らす人間全員のこと(キャリー)
キャリー:皆さんからたくさんのテーマといろいろな質問がでましたので、最後にいただいたご意見からお答えしていきたいと思います。補足しますと、今お褒めいただいたSIBLですが、さらに便利になります。ダイジェストに登場していたオランダ人の建築家が関わり、道の反対側に新装開店で引っ越します。もともとのSIBL発足の背景をお話ししますと、おっしゃられたようにウォールストリートの歴史、ウォールストリートでの仕事の中でのアーカイブという位置づけで立ち上げられました。ですが今では、SIBLは圧倒的に、会社をおこす・事業をおこすといった起業家精神のための一大中心地になっています。そして、具体例を出していただいたいろいろな講座やビジネスマン向けの活動をやっている訳です。映画本編に出ていないことを残念に思ってくださったことにもお礼申し上げます。確かに残念ですが、実は映画の中で出てくる分館は12か所しかありません。88か所のうちの12か所しか入っていない。私どもの誇りとしているSIBLも残念ながら落とさなければいけなかったのですが、今褒めてくださったことをSIBLの皆に伝言いたします。
資金についてですが、官民のパートナーシップというのは過去25年余に渡り、図書館だけではなく、いろいろな組織において重要な主流のやり方になってきています。1年の予算はおよそ3億7千万ドル。その約50%が、ニューヨーク市からの公的資金です。そして、年間2千万ドルがニューヨーク州のほうからの資金です。連邦政府からは元々いただいておりません。ましてや今の時代、いただかなくて当たり前という人選ですが(笑)。
研究図書館のために州からの2千万ドル。そして市からの資金。残りの資金は民間からいろいろなかたちで得ています。ニューヨーク公共図書館は、ブルックリンとクイーンズにもそれぞれの図書館網があり、そこと提携し、力をあわせて市長と市議会に対して予算折衝を行います。市当局へての働きかけというのは、はっきり申し上げてまったく楽しくありません。成果もなかなかあがりません。ブルームバーグ市長の時代には、基本的に市は「お金をくれない」「横ばい」「伸びない」、そうした状況が続いて、これを私たちはよく「ダンスを踊っている」と例えていました。ああ言えばこう言う、やりとりを重ねても、なかなか成果があがりませんでした。
今の市長になり、彼が掲げる重要目標と私たちがやっていることが見事に重なったことで、具体的な予算獲得につながっています。例えば市長は、政策の柱の一つとして、早期から読み書きを教えることを重要としていますが、私たちが、よちよち歩きの幼児から識字教室をやっていることで、市長としては公約を果たすことにつながる。これを大いに成果として主張して、予算獲得につなげています。
また、民間からと一口に言いましても、だいたい年間で合計1億ドルを、いろいろな方々──要するに政府以外──から、本当にありとあらゆる方からいただいています。5ドルくらいのごく少額でもずっと支えてくださる方もいらっしゃいますし、大々的に寄付してくださる方もいらっしゃいます。ありがたいのは、生きていく上でものすごく助かった、これで命がつながったと思ってくださる方々がいることです。
具体的に言いますと、ニューヨーク公共図書館があったから読み書きを身につけることができた、英語で読み書きができるようになったから仕事が見つかった、だから今生きている、今の自分がある、という方が、必ず何らかのかたちで返してくださっています。
そしてもう一つ、「公共=パブリック」の意味についても皆さんが説明してくださいましたが、端的に言いますと、皆の税金で支えているから皆のものだよね、ということです。パブリックというのは我々ニューヨークに暮らす人間全員のことを指しているということが、意識として、図書館は自分たちのものなんだ、皆のものなんだ、と思って下さっているんだと思います。
いろいろな財団、そして企業からお金を頂戴することもありますが、一番大きいのは個人からのご寄付なのです。これは篤志家からのチャリティ、フィランソロピーと言いますが、そうした慈善の一環として、どこかに資産を提供する、もしくは寄付をするというのは、アメリカのDNAの一部と言っても差し支えありません。また、あまり皆さんおっしゃいませんが、税金上有利だということもあります。今まで個人からいただいた最大のご寄付は1億ドルですが、5ドルくらいの寄付というのも大変ありがたいし、それも常時くださっている方々が沢山いるということは大事です。
そのために私どもは専門家のチームをかなり整備していますが、忘れてはいけないのは、民間からの寄付を募るというのは、もの凄く専門性の高い、そして時間もかかる、何年間もの関係づくりが必要だということ、断られてもめげない心の強さ、これが絶対必要だということです。お金の話で頭を使いきってしまいました。後の質問はピンポイントでいただくほうがいいかもしれません(笑)。
提供する側と利用する側の切磋琢磨でサービスが洗練される(菅谷)
野末:「図書館のおかげで生きられた」というのは重要だと思います。では、菅谷さんから、図書館の「情報」というときにとらえられているものが、ニューヨークのほうが広いのではないか、という話があったと思います。そこでいう情報の中には、マスメディア以外に図書館でつくりだしているものもありますが、人から受け取る情報みたいなものもあるのでしょうか。菅谷:人から受け取る情報というのは講演みたいなことでしょうか。アメリカの公共図書館のプログラムを考えれば、ダイジェストでみた講演はそんなに珍しくはないですが、先ほど、ニューヨーク公共図書館は自ら情報生み出している、と申しましたが、企画を立てて、図書館側が積極的に「これが必要とされているのでは」との発想から、どんどん新しいサービスを展開していくのは、恐らく日本の図書館と少し違っているのかなと思います。
お話しした舞台芸術図書館であれば、例えば舞台芸術は、なかなか文章にしたり、本でわかるような性質のものではないので、 図書館自らが舞台の様子を撮影し、それを貸し出したり、後世に残すべき監督やアーティストにインタビューして、それをコレクションにしていたり。確かにYouTubeなどにもいろいろな映像がありますが、 図書館の意義はやはり公益性の高いものを長期的な視点から集めてアーカイブできることです。YouTubeならば、ある時に消えてしまうことがあるかもしれませんが、公共図書館だからこそ、長く保存できるという強みもあると思います。
また、さきほど映像で出てきたピクチャー・コレクションですが、図書館の目利きが集めたものを、誰もが予約なしで使えるという、コレクションのアイデア自体も面白いですけれど、一方で、こうした資料からどんどんインスピレーションを得て、新しいものを生み出そうと、とことん使い倒しているユーザーの存在も大事だと思います。というのも、図書館は提供するサービスだけが良くても充分ではなく、それを使いこなすユーザーがいることも大事で、いわばボールの投げ合いというか、提供する側と利用する側に双方での切磋琢磨があるからこそサービスが洗練されていくからです。
だからニューヨーク公共図書館をニューヨーク公共図書館たらしめているのは利用者でもあると言えると思います。さらに、映画を見て分かるように、市民が必要としている情報は、「人力グーグル」のシーンにあった「ユニコーン」ではないですが、非常に幅広いことがわかります。
一方で、日本の図書館利用で一般的なのは、市民が本を借りて読み、そこから何か新しい知識を得るというような教養主義の色彩が強いものだと思いますが、それももちろん大事ですが、そこをさらに超えて、自らが暮らしていく上で、あるいは何かを成し遂げる上で、どんな情報を得て、何を実現し、そのためにどう図書館を使いこなしていくのか、という利用者サイドの意識を高めること、また、それに応えつつ図書館サービスを進化させるという、相互のあり方が大事だと思います。
利用者のニーズは「ご近所のさんのための図書館」だからこそわかる(キャリー)
野末:キャッチボールのように、利用者側のニーズを捕まえてサービスに反映して、そのサービスを受けて利用者が‥‥ということですね。キャリーさんにお伺いしたいのですが、利用者にこれだけ多様なサービスを提供している背景には利用者がどんなニーズを持っているかということを掴みにいく、分析するというプロセスがあると思いますが、どういった方針・方法で利用者のニーズ──こういう情報を必要としている、こういう活動を必要としている──を掴むのでしょうか。キャリー:かなり大きなご質問をいただいてしまいました(笑)。今のご質問に答えるのであれば、やはり分館についてお話するのがよいかと思います。もちろん研究図書館でもニーズを掘り起こす責務はありますが、研究者が必要としているニーズというのは全く性質の違うものですので。私たちは、分館のことを「ネイバーフッド・ライブラリー(neighborhood library)」と呼んでいますが、これは地域の中のご近所さんのための図書館といったニュアンスが入っています。それが分館の大きな特徴です。その分館はどこにあるのか。その地域の特性が分館にも大きく影響を与えます。
ニューヨークには低所得者もいる。ホームレスの問題もある。例えば、貧困層がいる地域では、どうしてもいろいろな面において行き届かなさがあり、その中で、どうやって皆さんをサポートできるのか、ということを重要な使命と位置付けています。
また、私たちが常に目指しているのは、その人自身がもっている最高の自分でいられるよう、それが実現できるようなお手伝いをたゆまず続けていくということです。その中で先ほど言った「ネイバーフッド・ライブラリー」という考え方が大事になってきます。ネイバーフッドにはその地域のご近所さん、その地域の仲間というニュアンスがありますが、その中の「コミュニティー・センター」として機能することです。映画をご覧いただければ分かりますが、この分館では、顔見知りの司書やスタッフのところへちょっと相談に行く、いつも利用者の皆さんとそういったやりとりをするということをしています。
ちなみに私たちは利用者を「パトロン」と呼んでいますが、それは「愛好者」という意味ですが、これは本当に常にここを使って下さる方々で、私たちにとって一番大切な存在です。私たちよりもパトロンを大切に中心にすえています。その皆さんが必要としている、欲しいと思っていることの全てに答えることはり無理ではありますが、その中で例えば、小ぢんまりとした、皆がくつろげる状況の中で識字教室をやる、また、アメリカならではのニーズかもしれませんが、大人になってから学ぶための英語教室をやる、仕事のためのいろいろな情報を提供する、ということをやっていく。場合によってはダンスをやりたい、編み物教室が欲しい、そういったことについても、できる限り機会をつくっていく。図書館がやることは、やはりそういった機会、そういった場を提供する、ということに他ならないかなと思っています。
越塚:ニーズ、あるいは困っていることに図書館が貢献するためのヒントを得ようとしているのだと思うんですが、映画には、比較的貧しい地域の図書館で、幹部の図書館員の方が、そこに集まってきた人たちの意見や表明することをひたすら聞き続ける、何も意見をさし挟むわけでもなく、それを評価するでもなく、ただただ聞き続けるという場面がでてくるんですね。おそらく、今(図書館を)使ってない人かもしれないけれども、困っていることがあるなら、図書館が何か役に立てるんじゃないか、そのヒントを得るために、人々の間に分けいっていくということ。実際に幹部職員、図書館員がやっている、そういうことを地道にされているんだというのも大変印象的でした。
日本で「ダンスをやりたい」と言われたら、図書館はやりますか(笑)(野末)
野末:いろいろなニーズをつかみ、あるいはリクエストがあって、ダンスとかロボットとかネット接続スポットの貸出しとか、どこまで応えるのでしょうか。我々が思っている図書館のイメージを越えたところもあるように思うのですが、ここまでは応えていこう、これは応えられない、というものはあるのでしょうか。日本で「ダンスをやりたい」と言われたら、図書館はやりますかね(笑)。キャリー:ぜひお試しください。楽しいですよ。ダンス教室は、あの地域の特定のニーズに答えたもので、決して全分館でやっている訳ではありません。大事なのは、図書館の組織全体で同じようにやっているものもあれば、特定の地域のニーズや要望に答えて特定のところだけでやっているものもあるということです。線引きにおいて重要な目安は、私たちはソーシャルワーカーではなく、あくまでも図書館ですので、社会福祉の分野に関わることは範疇外です。また、自由で、誰に対してもオープンで、誰でもウェルカムであるということは、市民社会の礎そのもの、根幹であって、誰であっても基本的にお断りはしませんが、あまりにも目に余るようなことをされた場合には、しばらくの間立ち入り禁止、ご遠慮いただくようにしています。ただそれは、とてつもなく悪い、とてつもなく非常識なことをされた方々の場合です。
そして、なぜ私たちがあれだけできるかというと、分館ごとのトップの人間にかなり自由裁量が与えられているからです。その地域のニーズやその地域の特性を一番知っているのは、本部よりも分館のトップでしょう、スタッフでしょう、という考え方でかなり任されています。もう一つは「ミッション・パッショネイト(mission passionate)」という言葉を使っていますが、ミッションに対してともかく情熱的に燃えている、入れ込んでいるスタッフばかりだということも大きいかと思います。私たちが何をやりたいのか、何をなさなくてはならないのか、ということについて、自分たちも一員として一丸となってやらなければならない、心底それに関わりたいという思いをもつ職員に恵まれていること。これが非常に大きいですし、献身的な働きに繋がっているのだと思います。
しかしそうは言っても、やはり、予算とか諸般の事情とか大人の事情で、NOというのは辛いのですが、どうしてもNOと言わざるを得ない場合も多々あります。予算の話楽しくないと申し上げましたが、かなり面倒くさいことをお話しますと、市からいただいている資金は分館でしか使えません。それも、分館なら何にでも使えるわけではなくて、分館の特定の目的だけのためにしか使えない、ひも付きのお金です。ですので、それ以外にやりたいことは自力でなんとかしなければならない、という問題を抱えています。
Wi-Fiのホットスポットの話をしますと、なぜあれが必要かというと、ニューヨーク市の人口900万人のうち250万人ほどが、実はブロードバンド接続でインターネットが使えない、自宅がそうした状況にあることがわかりました。なぜこれが問題なのかは、皆さんに伝わりづらいかもしれませんが、ニューヨークの公立学校に行っていて、ブロードバンド接続ができなかったら宿題ができません。子どもたちが学校で必要な課題をこなしていくためには、グーグル検索できなければならないけれど、映画のあの段階ではブロードバンド接続が不可能な状況だとできないものになっていた。
私たちはそういうニーズに気付いたので、それを助けようということで、電話会社と提携しました。そういった会社のご協力のおかげで---ちなみに端末1個につき35ドルの製造コスト---を使って、かなり強力なデバイスを提供していただけましたから、1世帯につき5人、場合によっては5つのアパートで共同してテザリングできる、という感じで使えるようにして、お蔭さまで非常にいいかたちで働いてくれたかなと思っています。
野末:田中さん、日本の図書館はどうしましょうか。ニーズにどう応えていくか、ということですが‥‥。
田中:これは私の考えですが、結局、情報や知識というものにアクセスできるということが、いかに個人として自立して、社会を支える一員として、人間らしく生きていくうえで、根幹だと思います。もっと生活レベルのことかもしれないですけど。それを支えていく役割は、この近代的な民主主義の中で、日本においても(ニューヨーク公共図書館と)当然同じだと思うんですね。やることというのは、個別事情において、今のお話のようにそれぞれ違うかもしれないですけども、「必要な情報を提供する」「オープンなかたちでアクセスを提供する」というその使命そのものは全くかわりないと。抽象的で申し訳ないですが、それは同じだという風に思います。
デジタル化も「情報、知識、機会を、全員に平等に対等に」の一環にすぎない(キャリー)
野末:デジタル化、ネットワーク化、モバイル化が進んでいて、ここまでのお話の中でもITもしくはICTへの対応は大きなキーワードになっていたかと思います。最近のニューヨーク公共図書館のデジタル化社会への対応、それに対する菅谷さんの捉え方、評価を少し補足いただけますでしょうか。菅谷:私よりキャリーさんの方が現状をご存知だと思うので、キャリーさんにお話いただくのが良いかと思いますが、例えば今ですとスマートフォンで30万冊の電子ブックがダウンロード可能など、かなり幅広いサービスが展開されていると思います。映画をご覧になった方が誤解されるかもしれないと思うのは、日本の図書館のデジタル情報提供がかなりゆっくり進んでいるので、映画を見て「凄い!」と感じられるかもしれませんが、映画が撮影されたのは数年前なので、今はもっと進化しています。特に分館のサービスは、生活に密着していると思うので、そのあたりの今を詳しく教えていただきたいです。
キャリー:実はニューヨーク公共図書館では、デジタルだから特別という考え方を全くしていません。124年間粛々とやってきたこと、つまり情報、知識、機会を、全員に平等に対等にアクセスできるような状況を整えていく。その一環の中のプラットフォームの一つにすぎないのです。これがまず出発点で、平常心でやっています。
私たちがやっている実際の成果としては、今、電子書籍がすごく伸びています。これは「テキストリーダー」ですが、「Simply-E」という特別なアプリを使って、皆さんに自由に貸し出せるようになっています。これには出版社とライセンスの交渉を激しくやらなければなりません。交渉の大変さは置いておくとして、電子書籍は今すごく人気がでていますし、ますます人気が出るでしょう。それ以外には、例えばWi-Fiスポットやルーターの貸し出しもありますし、あとはオンラインデータベースもあります。
あともう一つ自慢なのが、私たちのウェブサイト使って、ドキュメンタリー映画や芸術的なアートハウス系の映画のスリーミングサービスもやっています。どなたでもご覧いただけます。ただ、私たちのウェブサイトは本格的に作り直さなければならないなという気もしなくもありませんが。
揺るぎないミッションを軸にしつつも、時代やニーズの変化に応じてしなやかに(菅谷)
野末:菅谷さんはどうご覧になっていますか。菅谷:紙かデジタルかというのは、未だ日本で議論されていることかもしれません。おそらくニューヨーク公共図書館が、90年代半ばに議論していたようなことにまだ決着がついていないこともあるかもしれません。私は1995年からニューヨークに住んでいましたが、当時はまさにインターネットが一般に広まりつつある時期で、その頃からニューヨーク公共図書館は、新しい情報テクノロジーを一体どのように取り入れていくのかということに、興味をもって見てきました。そしてその過程でわかったのは、まさにキャリーさんおっしゃられたことです。
つまり、どのメディアで情報提供するのかが大事ではなく、市民に対してどんな情報をどう提供することでアクセスを保障していくかという、図書館のミッションを実現することです。そして、以来、根幹がぶれることなく、新しい時代の図書館としてどんどん進化してきました。
例えば、2000年を過ぎた頃に、米国でも大きな議論を呼んだグーグルブックスという書籍をスキャンし、デジタル化して全文検索を可能にするというプロジェクトがありました。ニューヨーク公共図書館は、ここに積極的に参加することで、サービスを強化しています。また、ネット経由での情報提供も積極的に行い、利用者も増えていますが、たとえ来館する人が減ることがあっても、大切なことは数ではなく、利用者にとってのサービスをいかに強化するかです。
一方で、物理的な空間に市民がやってくるような付加価値をつけたサービスも強化していて、映画にも出てくるような知の最先端をゆくようなスピーカーを招き、図書館でディスカッションをするなどプログラムも充実しています。同じような話を聞いても人々は異なる意見を持つのが当たり前ですから、図書館に会して違った意見に触れ、話し合うことで、コミュニティにいる人たちがどんな考えを持っているのか、講演を媒介に知ることができるような仕掛けです。
私がニューヨーク公共図書館を95年位からみてきて思うのは、ダーウィンが言ったとされる言葉にも通じます。「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」。つまり、揺るぎない図書館のミッションがあり、それを軸にしつつも、時代やニーズの変化に応じてしなやかにサービスを変えることができているからだと思うのです。ちょっと結論っぽくなりましたが、個人的にはそのように考えています。
デジタル時代の孤立ー物理的な場としての図書館は重要性を増している(キャリー)
キャリー:おっしゃる通りだと思います。デジタルの時代だからこそ一層その物理的な空間としての図書館の重要性というのは増すんじゃないかと、私たちはむしろ考えています。今のニューヨークで一銭も払わずに安心して時間を過ごせる場所というのは図書館くらいしかありません。そこに行けばコンピューターも自由に使える。お金を全く使わなくても安全だと思いながら時間を過ごすことができる。そういった場所であり続けるということはとても大事だと思っています。もう一点、デジタルの時代になってから一層、互いに孤立を痛感することが多くなったのではないかと思いますが、根本的に人間は社会を構成する生き物であるにも関わらず、ちょっと気を許すと自宅で独りぼっちでずっとスマホの画面を見ているような状況が当たり前になっている時代だからこそ、物理的な場としての図書館というのは、圧倒的に重要性を増していると思います。野末:情報と知識と機会を提供する──とても重要なポイントだと思います。お二人のお話にあったように、デジタルと物理的なものの特性、よさをうまく活かしていく、メディアの違いがどうこうではない、ということかと思います。越塚さん、「デジタルか紙か」について、我々はどうしましょうか。
社会との接点、社会を構成する場の提供に図書館は貢献できる(越塚)
越塚:基本的に私は大学で教えていますから、若い学生を相手にしていると、もう紙媒体は見ないですよね。そのことが良いか悪いかという問題はもちろんあります。最小努力の法則というのがありますが、人は何か与えられた状況で一番簡単な方法を選んで実行する。これは私が学生の時も言われましたが、今の学生を見ても全くそういう感じがします。紙媒体で調べたら、もっと多様な情報を調べられるのに、ということもあるけれど、スマホでチャチャっと調べて以上終わりにしてしまっている。過渡期と言われて久しいですが、まだまだそういう状況は続いているんじゃないかとは思います。けれど、その子どもたちの世代が図書館を利用するようになった時に、この環境のままでいいのかという疑問がありますね。一定水準以上の生活を送れるように時代を続けていくということを考えるならば、デジタル化は非常に重要なことだと思いますし、日本でも物理的な場に集えない人たちももちろんいるので、そのことに思いをはせることはやはり重要だと思います。
ただ一方で物理的に集まっていろいろ楽しむことは、キャリーさんも菅谷さんもおっしゃるように大変重要なことだと思いますから、どうやって引っ張り出してきて、社会とどのような接点を設けたり、社会を構成する場を提供するかというのは大変重要だと思いますし、意外といろいろ授業でやらせると面白がることは確かなんですね。だから図書館がそういう点で貢献できることは沢山あると思います。
私たちが学生の頃は、もう30年くらい前ですけれども、図書館というのは図書館だけの機能で成り立つのが一番良いのだという話があって、複合施設というのはあまり良くない、美術館とか博物館とか、(すごく離れた存在に思えるでしょうが)体育館などが一緒というのは良くないんだという話で勉強してきたように思います。しかし今、(いろいろな設備と一体化している図書館に)やっぱり人が集まるんですよね。
また、お互いに貢献することでより豊かなプログラムを提供できるというのは、工夫次第でいくらでもできると思います。武蔵境という駅前にある武蔵野プレイスとい図書館には、若者が沢山集まって、ある人たちは静かに本を読んでいるけど、ある人たちは卓球したり、ダンスをしたり、同じ建物の中で楽しんでいるというのは一つの典型的なパターンだと思います。もちろんすべてを図書館が運営している訳ではありませんけれど、そういうやり方もあるのかなと思います。図書館単体で何か考えるっていうのは、日本ではもしかしたら難しいかもしれませんけれど工夫のしようはあるのかなとは思います。
野末:無茶な振り方ばかりしてすみません(笑)。もう少し掘り下げて伺いたいこともあるのですが、会場の皆さんがうずうずされていると思いますので、皆さんから質問を受け付けるイマキクをオープンさせます。
「イマキク」での質疑応答はこちら
社会の変化の中、日本でも図書館サービスから恩恵を受ける人々は、多々いるはず(菅谷)
野末:では、まとめにかえて、パネリストの皆さまに一言ずついただきたいと思います。今日を振り返って、いかがでしたでしょうか。越塚:ぜひ映画を見ていただきたいと思います。どの立場の方もすごく得るもの、感じるものが沢山あると思いますので、とにかくご覧ください。
今年のALA年次総会がワシントンDCで開かれるのですけれど、そこで私たちのグループが日本の公共図書館のサービスを紹介するジャパンセッションを開くことができるようになりました。お金がすごくかかるのですが、公共図書館にはそのための予算というのは前例がありませんから、5月7日からクラウドファンディングをやろうということになりました。私たちは今回の機会のようにアメリカからいろいろな恩恵を受けるということはありましたが、日本から何かを提供するということが中々なかったと思います。
ですけれど、そういう双方向的な情報提供や意見交換をすることによっていろいろな新しい機運が生まれてくるんじゃないかということを期待していますので、ぜひご関心の向きはご協力いただければと思います。
田中:今日は本当に貴重な機会をいただいてありがたいと思いました。ここにいらっしゃるのは図書館関係の方が多いと思いますが、図書館が社会でどういう可能性をもっているのかということを本当によく分かる映画なので、図書館の外の人にも少しでも多く知っていただいて、図書館の理解者になってもらい、社会を変えていくための力になるように動いていくといいなと、心から願っております。
菅谷:この映画の冒頭に、ドーキンス博士の話が出てきますが、彼の話は色んな風に解釈ができます。「アメリカには無宗教の人が20%いるけれど、その存在がほとんど無視されている。それはなぜかというと、自分たちが認識されるように声を出していないからだ」、と話しています。ニューヨーク公共図書館のサービス対象は、移民してきたばかりで、米国での暮らしを立ち上げるために分館で英語を学んでいる人や、子供の学校関係のサポートが必要という人、クリエイティブな活動に研究図書館を利用するウディ・アレン監督みたいな方まで、随分異なるニーズの利用者がいるかと思います。
現在の日本の図書館が主なサービス対象としているのは、本を読んで知識を増やし教養を高める、あるいは研究調査を行なっている方々などへの支援などに思えますが、一方で今の日本社会は例えば30年前とは随分変わってきていると感じます。特に近年は、社会の格差が拡大していると言われているだけに、日本でも図書館サービスから恩恵を受ける人々は、多々いるはずです。
ところが、先ほどのドーキンス博士の話ではないですが、社会の中でそれが広く認識されておらず、あるいはそうした人々自らも、図書館からどう恩恵を被ることができるのかを知る機会もない可能性もあります。それだけに、図書館が率先してこうした人々に対してサービスを展開していくことも大切だと思います。さらに、ある程度クリエイティブな作業をする人たちに向けた情報の提供も必要で、新しい産業や芸術を生み出すには、そうした層に対する支援も必要かと思います。
とりわけ、終身雇用が崩れ、高齢化、共稼ぎ家庭、学校教育の課題など、社会問題が山積している中で、生活面においてさまざまな支援が必要な層に対する図書館サービスは、これからますます必要になっていくのではないかと改めて思いました。
野末:最後にキャリーさん、今日を振り返っていかがでしょうか。
キャリー:今、菅谷さんがおっしゃってくださったこと、すごく大事だと思います。完全に賛同します。そしてもう一言。ぜひ、ぜひ、映画ご覧ください。私は、夢にも思わなかった最高の仕事についていると、ありがたく思っています。夢のような仕事に関わることができている、そしてそういった中で皆さまに出会えたということがとても幸せです。この仕事についたおかげで、久々に日本に来られたことも嬉しく思っています。
野末:ありがとうございました。冒頭に申し上げたように、今日は皆さんにヒントやきっかけやひらめき、気づきを一つでも二つでも持ち帰っていただければ、お役目は果たせたかと思います。どうもありがとうございました。